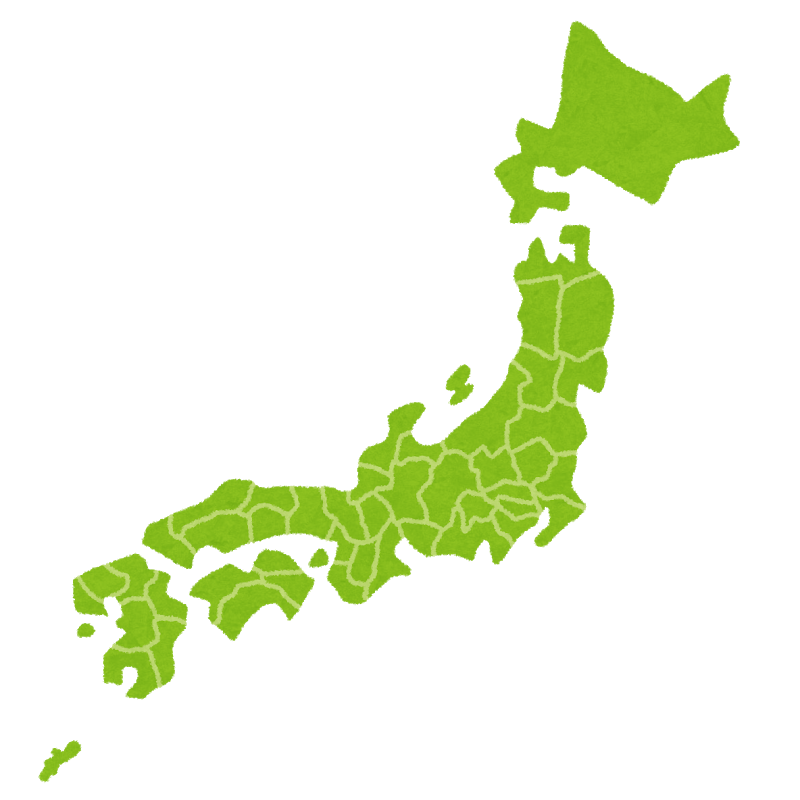近年、多様化する宿泊ニーズに対応するため、トレーラーハウスを活用した旅館業施設への関心が高まっています。本文書では、トレーラーハウスの法的位置づけから旅館業営業許可取得までの実務的なポイントを詳しく解説いたします
トレーラー・ハウスとは?
基本的な定義
「トレーラー・ハウス」とは、生活するための様々な設備を備えていて住居として使える車両で、それ自体には原動機がついておらず自動車で牽いて運ぶことができるものをいいます。ベッド、シャワールーム、キッチン(台所)、食卓などの他、サウナを備えているものもあります。英語圏では、「モービル・ホーム」や「トレーラー・ホーム」と呼ばれています。
電気・上水道・下水道(または浄化槽)などに接続して用いることもできる設計になっているものが多く、「タイヤ付きプレハブ住宅」と考えることも可能です。
トレーラー・ハウスとキャンピングカーの違いとは?
トレーラーハウスにもキャンピングカーにも、ミニキッチンやトイレなどが備わっています。設備や用途の点では類似していますが、以下の重要な違いがあります。
動力装置の有無
- キャンピングカー:それ自体に原動機(エンジン)を搭載しているため、単独で走行が可能
- トレーラーハウス:それ自体には原動機がついておらず、ピックアップトラックなどの自動車で牽引しなければ移動できない
インフラ接続能力
- キャンピングカー:上水道・下水道などに接続できないため、水をタンクにためて対応
- トレーラーハウス:上水道・下水道(または浄化槽)などに接続可能
トレーラー・ハウスは「建物」ではなく「車両」
「建物」か「車両」かの判断基準
適法に公道を移動できるものは「車両」に該当するため、トレーラーハウスも適法に公道を移動できる状態であれば「車両」にあたります。逆に、適法に公道を移動できない状態の「トレーラーハウス」は車両とはいえないため、「建築物」として扱われてしまいます。
この判断は旅館業営業許可において極めて重要な要素となります。
建築基準法との関係
基本的な判断基準
平成9年3月31日建設省住宅局建築指導課長「建設省住指発第170号」によれば、トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス、電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号の規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこととされています。
建築物として扱われる具体例
この通知で示された要件の内容を整理すると、次のようなものは「車両」ではなく「建築物」として扱われます。
- 構造物の設置
トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの - 設備接続方式
給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの - 物理的移動可能性
その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるものとは認められないもの
設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通じて土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該トレーラーハウス等を建築物として取り扱うことが適切とされています。
- トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。
- 給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の為の設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。
- その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるものとは認められないもの。
なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通じて土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該トレーラーハウス等を建築物として取り扱うことが適切である。
日本建築行政会議『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』2017年度版
「随意かつ任意に移動できるとは認められないもの」とは?
平成9年3月31日建設省住宅局建築指導課長「建設省住指発第170号」で示された「随意かつ任意に移動できるとは認められないもの」という基準は不明確であるため、その内容について日本建築行政会議では以下のように具体例を挙げて解説されています。
「随時かつ任意に移動できる」の具体的基準
- 車輪の状態
車輪が取り外されているもの
車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの - 支持構造
上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等) - 移動経路の確保
トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)がないもの - 許可の性質
臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできない
- 車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。
- 上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。
- トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)がないもの。
臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできない。
日本建築行政会議『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』2017年度版
道路運送車両法との関係
臨時運行の許可
トレーラーハウスを運行するためには、道路運送車両法第34条に基づく臨時運行の許可を受ける必要があります。
道路運送車両の保安基準と基準緩和制度
道路運送車両の保安基準第2条では、車両は長さ12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならないと定められています。トレーラーハウスは、このような自動車の大きさに関する制限の他、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、以前は原則として運行の用に供することができませんでした。
しかし、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗・事務営業所・公共施設等として利用したいとの要望が多く寄せられたため、移動が限定的なトレーラーハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度が改正されました。
平成24年に改正された「道路運送車両の保安基準」第55条第1項に基づく基準緩和認定制度により、トレーラーハウスを一時的に運行できるようになっています。
建築物を新築できない場所でもトレーラーハウスは設置可能
市街化調整区域での設置可能性
都市計画法では、計画的なまちづくりをするために「市街化区域」や「市街化調整区域」が規定されています。
市街化区域 すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(都市計画法第7条第2項)
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域と規定されており、原則として新たな開発・建築行為を禁止し、市街地の無秩序な拡散を抑制する区域(法第7条第3項)
したがって、市街化調整区域では、原則として新たに建築物の建築を行うことができず、旅館業施設のために建築物を新築することもできません。
トレーラーハウスの優位性
しかし、トレーラーハウスは前述の通り「建築物」ではなく「車両(自動車)」に該当するため、トレーラーハウスを設置することに関しては都市計画法の制限を受けません。これにより、通常の建築物では建設が困難な立地でも旅館業施設の運営が可能となります。
トレーラーハウスに浄化槽を設置できるか?
浄化槽設置の必要性
トレーラーハウスは建築物を建築することが困難な場所にも設置することが容易であるため、上下水道が整備されていない場所に設置したいという要望が多く寄せられています。そのようなケースで重要となるのが「浄化槽」の設置です。
浄化槽の法的位置づけ
通常の浄化槽設置
浄化槽は、通常は住宅に対して設置することが想定されています。例えば、JISでは建築物の用途別に「し尿浄化槽の処理対象人員算定基準」を規定しており、住宅と宿泊施設ではその算定式が異なります。
浄化槽設置の手続とは
浄化槽を設置・変更・廃止する際には、自治体に届け出を行う必要があります。家屋等の新改築に伴う浄化槽設置の場合には、建築基準法に基づく建築確認申請と合わせて届出を行います。
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項の規定により建築主事に通知すべきときは、この限りでない。
浄化槽法第五条(設置等の届出、勧告及び変更命令)
建築物がなくても浄化槽を設置できるか?
誤解される理由
住宅や宿泊施設をはじめとする「建築物」に浄化槽を設置する場合は、建築基準法に基づく建築確認等の審査が必要ですが、随時かつ任意に移動できる状態のトレーラーハウスは建築物とは認められないため、建築基準法に基づく人槽算定等の審査対象となりません。
そのため、トレーラーハウスには浄化槽が設置できないと誤解している事業者もいます。
設置可能性
しかし、浄化槽で処理対象とする排水の排出対象施設は、浄化槽法において建築物に限定するものではないため、トレーラーハウスに接続する場合においても、以下の条件が満たされれば設置が可能と考えられます。
- トレーラーハウスを撤去や移動に伴い排水管を分離する際の浄化槽廃止手続きと撤去が確約されること
- 浄化槽法の規定に基づく設計
- 浄化槽設備士の監督による配管等を含めた設置施工、保守点検・清掃・検査受検等の維持管理の履行が確実に確認可能であること
届出時の留意点
したがって、トレーラーハウスに浄化槽を設置する場合には、以下の事項を疎明する資料を添付しながら自治体に届出をすることにより対応します。
- 届出時の留意点
浄化槽法の規定に基づき浄化槽を設計していること - 維持管理体制
浄化槽設備士の監督による配管等を含めた設置施工、保守点検・清掃・検査受検等の維持管理の履行が確実に確認可能であること - 撤去計画
トレーラーハウスを撤去や移動に伴い排水管を分離する際の浄化槽廃止手続きと撤去が確約されていること