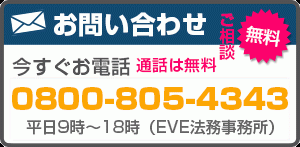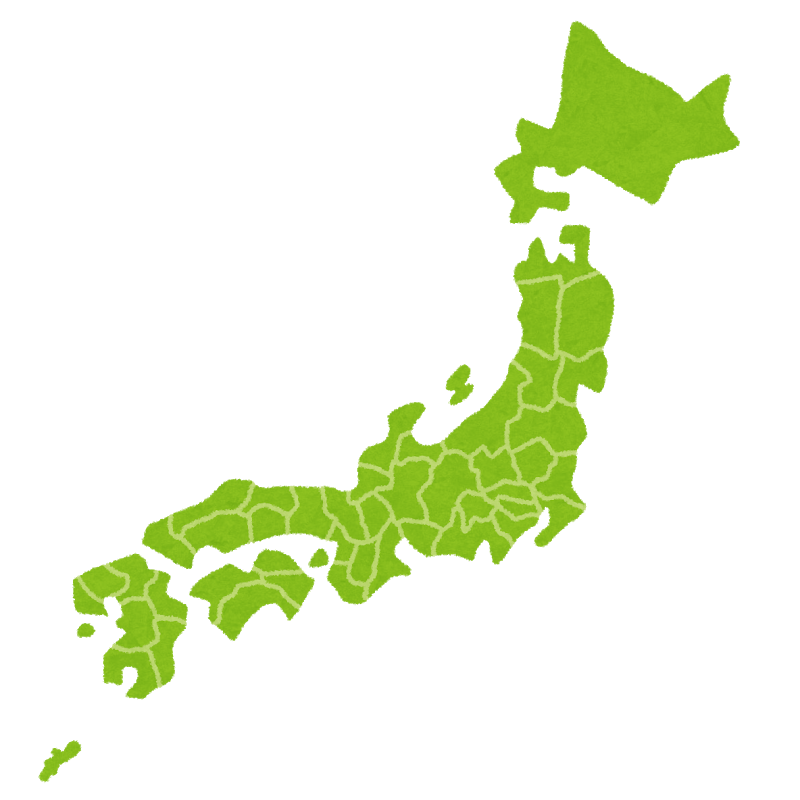日経新聞で、「農家民宿」についての記事が掲載されていました。弊所では、以前からセミナー等で農家民宿の仕組みを利用した民泊について提案してきましたが、改めて本記事で取り上げたいと思います。
[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””] 大手旅行各社が農業で地方の観光市場を開拓する。近畿日本ツーリストを傘下に抱えるKNT―CTホールディングスは、農園を使った新型リゾートの経営に参画。日本旅行は農業体験を組み込んだ修学旅行を企画する。各社は訪日外国人を含む誘客の伸びしろは地方にあるとみている。農業を魅力ある観光資源として磨き、旅行需要を底上げする。2016/8/18付日本経済新聞 朝刊
[/ip5_coloredbox]平成28年4月より旅館業法の運用が変わりましたが、世間の注目は簡易宿所の「面積要件緩和」や「構造設備基準の緩和(玄関帳場に関する規定)」にばかり集まっていました。当時の新聞記事等でも、この2点について扱ったものばかりでした。
しかし、平成28年4月から実施された旅館業法の運用変更では、「農村余暇法」で規定される「農家民宿」についても重大は変更が実施されています。今回はこの点について解説します。
[ip5_box size=”box–large” title=”平成28年4月からの変更点” title_size=”” width=””]- 簡易宿所営業の要件を緩和
- 客室の延べ床面積要件を緩和
- 収容定員が10人未満の場合は一人あたり3.3㎡以上
- 農家民宿の主体制限を撤廃
- 旅館業法施行令を改正
- 「農林漁業者が」という主体についての文言削除
「農家民宿」とは、農村余暇法(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律)2条5項で規定されている「農林漁業体験民宿業」の通称で、旅館業法上の「簡易宿所」のうち、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。)に必要な役務を提供する営業をいいます。
平成28年3月までは、農家・漁業者・林業者しか開業できませんでしたが、平成28年4月からは主体制限が廃止されました。
[ip5_box size=”box–large” title=”農家民宿とは” title_size=”” width=””]- 旅館業法上の「簡易宿所」のうち、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業
では、農家民宿で「必要な役務」とは何があるのでしょうか?これは、農村余暇法施行規則で規定されています。
[ip5_box size=”box–large” title=”農家民宿の「必要な役務」とは” title_size=”” width=””]- 農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
イ 農作業の体験の指導
ロ 農産物の加工又は調理の体験の指導
ハ 地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与
ニ 農用地その他の農業資源の案内
ホ 農作業体験施設等を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん - 山村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
イ 森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導
ロ 林産物の加工又は調理の体験の指導
ハ 地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与
ニ 森林の案内
ホ 山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん - 漁村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務
イ 漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導
ロ 水産物の加工又は調理の体験の指導
ハ 地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与
ニ 漁場の案内
ホ 漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん
上記で列挙された役務をみると実現が困難なように感じられるかもしれませんが、実際にはとても簡単です。弊所では、各項にある「へ 前各号に掲げる役務の提供のあっせん」を活用することにより、無理なく農家民宿の要件をクリアするノウハウを提供しています。
また、この農家民宿の枠組みを活用することで、簡易宿所型民泊のネックとなっていた点がほぼ全て解消される特例措置を受けられます。
[ip5_box size=”box–large” title=”農家民宿の特例(一部)” title_size=”” width=””]- 旅館業法
- 構造設備基準の緩和
- 建築基準法
- 「旅館」に該当しない
- 消防法
- 誘導灯・火災報知設備等が設置不要
インバウンドツーリズムが新たなフェーズに入り、農家民宿を活用した体験型ツーリズム需要が増大することは確実です。農家民宿の仕組みを活用した民泊に参入する企業も増えると見込まれます。
[ip5_coloredbox color=”colored-box–green” width=””]都市住民を農山漁村に呼び込む狙いから1995年に農山漁村余暇法が施行された。農林水産省の調査によると、農産物直売所が年9000億円を超える市場を形づくるなか、農業体験ができる観光農園の市場は約360億円、農家民宿は約50億円にとどまる。農村体験を組み込んだ旅行の本場とされる欧州と比較すると、まだ伸びる余地はあるとみられる。
2016/8/18付日本経済新聞 朝刊
[/ip5_coloredbox]農家民宿の主体制限解除については保健所の旅農林漁業体験民宿業」館業担当者でも知らないケースが多く、弊所クライアントの中にも保健所で誤った指導を受けたケースが多数あります。
農家民宿については、全国で実績豊富な民泊専門の弊所へご依頼ください。